「足場に張るメッシュシートはどれを選べばいいのだろう?」
「できれば見た目もスッキリさせたいし、でもコストも抑えたい……」
足場を自社で組むことを検討しているなら、メッシュシートについても考える必要がありますよね。
けれど、いろいろ種類がある中でどれを選ぶべきかわからず、困っていませんか?
結論からお伝えすると、総合的に見ておすすめのメッシュシートは、次のような仕様のものです。
| メッシュシートのおすすめ仕様 | |
|---|---|
| 分類 | 2類 |
| サイズ | 1.8m幅 |
| 目合い | 1〜2mm程度 |
| 色 | 黒 |
メッシュシートは単なる「覆い」ではなく、現場の安全性・快適性・作業効率に直結する資材です。
たとえば、風の強い地域で目の細か過ぎるシートを使えば足場全体に大きな負荷がかかります。
採光性や透過性の低いシートを使えば、施工対象の建築物の住人から苦情が出る可能性があります。
機能性を考慮せずに「安ければいい」「とりあえず使えればいい」といった考えで選んでしまうのはおすすめできません。
さらに、メッシュシートはその機能面もさることながら、見た目にも配慮する必要があります。
著しく汚れていたり、隣り合う面で目合い(網目の細かさ)が異なったりすると、機能的には問題がなくても見栄えが悪く、施主や元請けに良い印象は持ってもらえないでしょう。
そこで本記事では、はじめて足場用メッシュシートを扱う人に向けて、知っておくべき基本知識から注意点、おすすめ仕様、相場、購入先までを一挙解説します。
本記事をお読みいただくことで、「自社にはどんなメッシュシートが最適か」が明確になり、自信を持って判断できるようになるでしょう。
ぜひ最後までお読みいただき、自社にぴったりのメッシュシートを選ぶためのヒントを手に入れてください。
1. 足場で使うメッシュシートの基本

外壁塗装などの建設現場で、足場に張られているメッシュ状のシート。
当たり前のように現場で使われているこの「メッシュシート」ですが、その素材や性能、設置の目的には明確な理由と基準があります。
そこで本章では、以下基本の3つについて解説します。
「足場に張っておくもの」として無意識に選ぶのではなく、自社に合ったものを選ぶため、まずは以下でメッシュシートの役割や関連法令をしっかり理解しておきましょう。
1-1. 足場用メッシュシートとは
メッシュシートとは、足場に張ることで作業中の安全性や環境対策をサポートする、網目状の養生シート(設置された足場を覆うシート)です。

メッシュシートの主な役割は、次の2つです。
- 落下物による災害防止
- 塗料・洗浄水などの飛散防止
建設現場では高所で作業が行われるため、工具や部材が誤って落下するリスクや、洗浄・塗装作業時に水や塗料が周囲に飛散するリスクがあります。
これらは現場の職人だけでなく、歩行者や近隣住民にも危険や不快感を与えかねません。
たとえば、高圧洗浄中に飛んだ水滴が隣家の洗濯物を濡らしたり、風で飛んだペンキの飛沫が車を汚したりといったトラブルは、現実に多く報告されています。
さらに、上記2つの主要な役割に加え、
- 現場内部の様子を外部から見えにくくする
- 強い陽射しや風を遮る
- 作業員墜落時に一気に地上まで落下するのを防ぐ
といった副次的効果もあります。
作業者自身の安全の確保、トラブルの防止、作業効率の向上の手段として、養生シートの中でもメッシュシートは現場に欠かせない存在となっています。
| メッシュシートを含む養生シート全般については、下記の記事で詳しく解説していますので、気になる方はぜひご参照ください。 ▼足場には養生シートが必須?役割・法的な必要性・種類と対応する現場 |
1-2. 足場用メッシュシートの規格
足場用メッシュシートには、建設現場での使用を前提としたJIS(日本産業規格)や仮設工業会の認定基準があります。具体的には、下記に挙げるような各種条件を満たしていなければなりません。
- 合成繊維製である
- 規定されている引張強度を有している
- 規定されている防炎性を有している
- 規定されている耐貫通性を有している 等
[参考]
日本産業企画 JIS A8952「建築工事用シート」(※閲覧するには無料利用者登録が必要です)
一般社団法人仮設工業会|認定基準の一部改正について
したがって、商品選定の際には、必ず仮設工業会の認定品であるかどうかを確認しましょう。
1-3. 足場用メッシュシートに関係する法令
明確に「足場にはメッシュシートを張りなさい」と規定する法令はありません。
したがって、足場にメッシュシートを張らないからといって即法令違反となるわけではありません。
しかし、実情としては、メッシュシートの使用は現場運営上ほぼ必須といえます。
なぜなら、法令で義務づけられている危険防止措置を取る上で、メッシュシートはもっとも現実的な選択肢だからです。
以下に、関連法令をまとめてみました。
| 法令 | 定められている内容 |
|---|---|
| 労働安全衛生規則 第563条第1項第6号(厚生労働省) | 落下物による危険防止措置として、以下に挙げるようなものを設置する。
|
| 建設工事公衆災害防止対策要綱 第2章第23項第2号(国土交通省) |
工事等を行う部分から、ふ角 75 度を超える範囲または水平距離5m以内の範囲に建築物等がある場合、落下物による危険防止措置として防護棚等を設置する。 |
| 足場先行工法のガイドライン 5-(13)-ロ(厚生労働省) |
棟上げ後は、落下・飛来物による災害防止のため、シート等を設置することが望ましい |
法令で定められているのは、あくまで「何らかの危険防止措置」であり、その手段としてメッシュシートが指定されているわけではありません。
つまり、メッシュシートの代わりに金網などでも対応可能なのです。
しかし、コストや作業性、周囲への影響を考慮すると、養生シートが最適解であり、養生シートのなかでも手軽で、利便性の高いメッシュシートが選ばれることが多いのです。
実際に、特に外壁塗装の現場では、足場にはメッシュシートを張るのがスタンダード。張らなければ、クレームの原因となったり、元請けやお客様からの信頼を損なったりするでしょう。
明確な法的義務ではないといっても、メッシュシートは今や現場における「事実上の必需品」です。
2. 足場用メッシュシートの特徴から見るメリット4つ

メッシュシートはあくまで養生シートの一種ですが、圧倒的に支持されており、多くの現場で採用されています。
その理由はもちろん、メッシュシートには多くのメリットがあるからです。
| 足場用メッシュシートのメリット4つ |
|---|
|
もう少し詳しく確認していきましょう。
2-1. 【メリット1】風の抵抗を受けにくい
風抵抗を受けにくく、足場の安定性を保ちやすいという特性は、メッシュシートの大きなメリットです。
網目を通して風を逃がす構造のため、目の詰まったシートに比べて帆のように風をはらみにくく、強風による足場倒壊リスクを低減できるのです。
特に風の影響が大きい海沿いなどにある現場では、メッシュシートを使うことで足場の安全性と耐久性が格段に向上します。
足場への負荷を抑えられるというこの特性は、風が強い高所での現場はもちろん、一般的な建設現場でもメッシュシートが選ばれることの理由となっているといえます。
2-2. 【メリット2】採光性・視認性・通風性が高い
採光性・視認性・通風性の高さも、メッシュシートの持つ優れた特性です。
網目構造がもたらすこれらの特徴は、作業員のパフォーマンス維持につながり、作業効率や安全性の改善に貢献します。
| 特徴 | 作業員にもたらされる効果 |
|---|---|
| 採光性が高い(光を通す) | 足場内部に自然光が届きやすく、手元が明るい |
| 視認性が高い(視界がある程度確保される) |
|
| 通風性が高い(風が自然に抜ける) | 熱や湿気が溜まりにくく、体力的・精神的な負担が軽減される |
また、こうした特徴から、室内に住人がいる状態での施工となる現場では住民への配慮としても、メッシュシートが活躍するのです。
採光性・視認性・通風性の高さは、足場で高所作業を行う作業員にとっても、室内の住人にとっても、大きな利点となります。
2-3. 【メリット3】軽くて扱いやすい
軽くて扱いやすいことも、メッシュシートのメリットの一つです。
網目構造であるため、目の詰んだ生地よりも軽量で、柔軟性にも優れているのです。
たかがシートとはいえ、足場を覆うサイズ感であるだけに、しっかりとした厚手のシート(特に防音シート)であれば、その重量はかなりのものとなってしまいます。
その点、メッシュシートは比較的軽量で取り回しが良く、設置作業もスムーズに行えます。
軽くて扱いやすいというメッシュシートの特徴は、作業効率と安全性の両方に貢献しているといえるでしょう。
2-4. 【メリット4】比較的安価
比較的安価であることも、メッシュシートの見逃せないメリットの一つです。
基本的に単一の素材から作られ、構造もシンプルであるため、ラミネート加工されて多層構造となっている防音シートなどに比べて製造にコストがかかりません。
メッシュシートと防音シートの価格相場を比較したものが下表です。
| 価格相場の比較 | |
|---|---|
| メッシュシート(2類)* | 1,500〜3,000円程度 |
| メッシュシート(1類)* | 7,000〜12,000円程度 |
| 防音シート | 5,000〜20,000円程度 |
| *メッシュシートは「1類」「2類」の2種類に分類され、強度は「1類>2類」となっています。 詳細は「3-1. 強度による分類」にて解説しています。 |
足場を覆うためには何枚ものシートが必要ですので、現場全体で見ると1枚当たりの価格差が予算に大きく影響します。
(※使用枚数目安については「4. 足場用メッシュシートの価格相場と枚数・費用シミュレーション」にて解説しています)
低コストで導入しやすいというメッシュシートの利点は、予算への負担を常に考えなくてはならない現場事情において重要です。
3. 足場用メッシュシートの使用における注意点

足場用メッシュシートは、前述の通り非常に使い勝手の良い養生シートですが、以下のような点に注意が必要です。
- 防塵性能は限定的
- 防音効果はほぼない
- 強度が高くない
- 遮蔽性に欠ける
言われてみると当たり前のことのようですが、ここの認識が甘いと、つい「本来は防音シートを貼るべきところを、メッシュシートだけで済ませてしまった…」という現場につながりかねません。
適切な養生ができていないと、近隣トラブルにつながりやすくもなります。
これらを踏まえて、現場に求められる養生を適切に行う必要があることを、今のうちにしっかりと理解しておきましょう。
3-1. 防塵性能は限定的
メッシュシートは網目上のため、防塵性能は当たり前ですが限定的です。
足場を完全に覆っても、ごく微細な粉じんや砂埃までは防ぎきれません。
解体現場など大量の粉じんが飛散する現場では、メッシュシートだけでは細かい粉じんが風に乗って周辺エリアに舞い上がる可能性があります。
そのため、そういった現場では
- メッシュシートを二重に張る
- 防塵用のシートを追加設置する
- ラミネート加工されている防音シートを使う
といった対応を取る必要があるでしょう。
網目構造であるメッシュシート単体では、高い飛散防止効果は望めません。
3-2. 防音効果はほぼない
メッシュシートに防音効果はほとんどありません。
網目が空いている構造のため、音は遮られず、そのまま漏れて周囲に伝わってしまいます。
解体工事現場のように騒音対策が重要な現場では、遮音性のある防音シートを使用する必要があります。
【参考】
国土交通省|建設工事に伴う騒音振動対策技術指針
環境省|騒音規制法の概要
東京都環境局|建設工事に係る騒音・振動の規制 簡易表
周囲に人家が全くないような現場であればその限りではありませんが、特に大きな騒音が発生する解体現場では、メッシュシートだけ張るという養生方法は不適切です。
▼合わせてこちらもご覧ください▼
足場に貼る防音シートは解体工事に必要不可欠!効果とおすすめ仕様
3-3. 強度が高くない
メッシュシートは、網目状ではなく密度の高い防音シートに比べ、強度が劣ります。網目構造で繊維同士の交点部が少なく、単層構造でもあるためです。
引張りや突起への耐久性が比較的低く、飛来物が当たる、木の枝が引っかかるなど、無理な力がかかったときに破れやすいです。
「重量物の落下リスクが高い鉄骨工事の現場」など養生シートに強度が求められる現場には、メッシュシート単体での使用はおすすめできません。
3-4. 遮蔽性に欠ける
メッシュシートは遮蔽性に欠けます。
網目を通して外の景色がある程度透けるため、外部からの視線を完全には遮断できません。
プライバシー重視の現場や、完成まで目隠ししておきたい現場などでは、遮蔽性の高い不透過シートや、視界を完全に遮れる防音シートやパネルを使います。
「防犯対策が求められている」「できるだけ中が見えないようにしてほしいという施主から依頼あり」などの理由で視線を遮断する必要がある現場には、メッシュシートは向いていません。
| その他:足場用メッシュシートのメンテナンスはクリーニング業者の利用がおすすめ |
|---|
| 足場でメッシュシートを使用していると、当然ながらどんどん汚れていくため、適切なメンテナンスが必要です。 メッシュシートは足場全体を囲っているため、非常にビジュアル面で大きな影響があります。 ひどく汚れていたり、状態が悪いものをそのまま利用していると、周囲の人にネガティブな印象を与えかねません。 足場用メッシュシートを自社で購入し使う場合は、自分たちで洗濯するのは非常に大変なので、都度建築用シートやネットを専門に扱うクリーニング業者に洗ってもらうなどして、しっかりとメンテナンスをしていくことが望ましいです。 |
4. 足場用メッシュシートの各仕様とおすすめの組み合わせ

メッシュシートのメリットとデメリットを見てきましたが、メッシュシートとひと口にいっても、実はさまざまな種類があります。
メッシュシートを選ぶ上で押さえておきたいポイントとしては、以下の4つです。
- 強度(1類・2類)
- サイズ
- 目合い(網目の細かさ)
- 色
そして、結論をお伝えすると、総合的に見ておすすめのメッシュシートは、この4つの項目の組み合わせが下記のようになっているものです。
| メッシュシートのおすすめ仕様 | |
|---|---|
| 分類 | 2類 |
| サイズ | 1.8m幅 |
| 目合い | 1〜2mm程度 |
| 色 | 黒 |
とはいえ、上でご紹介している組み合わせは、あくまで「バランスが取れている」というもの。
目的や現場の状況によって最適な仕様は変わってきますので、以下で各項目について確認しておきましょう。
4-1. 強度(1類・2類)
メッシュシートは、強度によって「1類」と「2類」に分けられています。
違いは下表の通りです。
| 1類 | 引張強度、耐貫通性などが2類より高く、堅牢。 大規模な新築現場やゼネコン案件での指定が多い。 |
|---|---|
| 2類 | 強度は1類に劣るが、コストパフォーマンスに優れる。 小〜中規模の現場や外壁塗装現場などで広く使用されている。 |
足場用資材などの落下の危険性があれば1類が適当ですが、たとえば戸建て住宅の外壁塗装で使うのであれば、塗料の飛散防止目的ですので、2類でまったく問題ありません。
とはいえ、元請けから「1類を使用してください」と指定があれば、そちらを使う必要があります。
多くの場合、基本的には2類、要請があれば1類といった使い分けとなるでしょう。
| ワンポイント
1類は2類に比べ強度が高い分、価格が高いです。使用頻度もそこまで多くないため、1類メッシュシートは購入するのではなくレンタルで対応する業者は少なくありません。 |
1類と2類という分類については、下記の記事でより詳しく解説していますので、ぜひそちらもご参照ください。
▼足場には養生シートが必須?役割・法的な必要性・種類と対応する現場
4-2. サイズ
メッシュシートには複数のサイズ展開がありますが、もっとも広く使われているのは、幅1.8m(インチサイズの場合は1,829mm)のものです。
足場の1スパンの長さの主流が約1.8mであるため、無駄なく張れるサイズがこの幅というわけです。
長さ方向については、足場の高さに合わせることになります。
たとえば、くさび足場(1段の高さが1.8m)を使用している業者が戸建て住宅の現場メインで使用する場合は、3.5段で組むことが多いため、
1.8m×3.5段=6.3m
ということで、1.8m×6.3mサイズが売れ筋です。
迷ったときは、まず幅1.8mのものに絞り、その中から自社の組む足場に見合った長さのものを選びましょう。
4-3. 目合い(網目の細かさ)
メッシュシートは、目合い(網目の細かさ)にも幅があります。
カタログ上では「充実度」で表示されることが多く、数値が高いほど目が詰まっています。
風通しや遮蔽性に関わってくるため、飛散防止や通気性といった複数の要素のバランスを考慮して選ぶことになりますが、目合い1〜2 mm程度のものが採用されることが多い傾向です。
「今回は飛散量が多そうだから……」などと現場ごとに使い分けるというよりは、同じものを使い続けるのが一般的です。
目合いの異なるシートを隣り合わせて使うと、遠目で見たときに継ぎはぎのように見えてしいまい、見栄えがよくないからです。
せっかくきれいに塗装・施工しても、建物全体の印象が悪くなってしまっては残念ですよね。
基本的には同じ目合いのものを継続して使っていくという前提で、「防塵性を最重視」「視認性にこだわりたい」など優先順位をつけて最初の1セットを選ぶのがおすすめです。
4-4. 色
色は機能面だけでなく、見た目やブランディングにも関わる重要な要素です。
主に白、グレー、緑、水色、黒などが展開されていますが、1類ではグレーが人気色、2類メッシュシートは黒が圧倒的に主流です。

昔は白・緑・黄色といった色も使われていましたが、現在の現場では、2類はほぼ黒一択といっても過言ではありません。
黒は汚れが目立たないこともありますが、光の乱反射が少ないため、外の景色がある程度透けて見え、室内も明るく感じられることから、住人が居住している状態で施工を行う現場では特に好まれます。
その一方で、分譲地などの新築工事では、元請けから「現場全体を水色で統一して」などとブランディングのための色指定があるケースもあります。
新築の場合、中にまだ人が住んでおらず、採光性や透過性に配慮する必要がないため、コーポレートカラーなどに統一するのは確かにアイデアとして優れているといえるでしょう。
何色にしようか…と悩んだら、基本的には黒を選んでおくのがおすすめです。
| 採光性に優れた高透明度のメッシュシートも登場 |
|---|
| かつては「メッシュシート=薄暗い」という印象もありましたが、近年では採光性に優れたメッシュシートが登場しています。 「ライトクリアメッシュ」といった名称のこうした商品は、非常に透明度が高く、まるで窓のように光を通します。部分的にこのシートを使うことで、現場内をより明るく保つことも可能です。 特に、建物内に人がいる場合や、明るさが作業性に影響する現場などでは、採用を検討する価値があるといえるでしょう。 |
5. 足場用メッシュシートの価格相場と費用シミュレーション

メッシュシートのメリットや注意点、種類などが把握できたところで、価格相場についても確認しておきましょう。
メッシュシートの価格は、網目の密度や寸法、厚みなどによって変わってきますが、購入する場合とレンタルする場合それぞれのおおよその価格相場は下表の通りです。
| メッシュシートの価格相場 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 購入する場合の価格相場 | レンタルする場合の価格相場* |
| 1類 | 8,000〜20,000円/枚 | 1日当たり数百円/枚 |
| 2類 | 2,000〜5,000円/枚 | |
(*レンタルする場合の価格は都度見積もりとなる場合が多く、さまざまな要素により価格に幅が出ると考えられるため、特におおまかな目安となっています)
たとえば、一般的な2階建て戸建て住宅の外壁塗装工事で必要となるメッシュシートの枚数と費用目安をシミュレーションしてみましょう。
| 延床面積35坪(建坪17.5坪)の2階建戸建て住宅の 外壁塗装工事で必要となるメッシュシートの枚数・費用試算* | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 必要枚数目安 | 想定単価 | 費用目安 |
| 1類購入 | 27枚前後 | 8,000〜20,000円/枚 | 216,000〜540,000円 |
| 2類購入 | 2,000〜5,000円/枚 | 54,000〜135,000円 | |
| レンタル | 100〜300円/日 | 14日間レンタルする場合 37,800〜113,400万円 | |
*枚数・費用試算の詳細:
よって、必要なメッシュシートの枚数は約27枚となる。 |
1類を購入する場合、ひとつの現場で使用する分だけでも数十万円単位のコストがかかることがわかります。
1類メッシュシートはレンタルで調達するケースが多いと前述しましたが、その理由が理解できる試算結果といえそうです。
1類に比べずっと安価な2類の場合は、半月以上使うならレンタルではなく購入するほうがかえってコストを抑えられるケースが増えてきます。
個々の商品の価格差のほかに、どこで買うかによっても計算条件は変わってきますが、ざっくりとした費用感としてご参考になさってください。
▼合わせてこちらもご覧ください▼
足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較
足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!
6. どこで買うのがおすすめ?足場用メッシュシートの購入先

メッシュシートは何枚も使う資材ですから、「どこで買うか」がコストに影響してくるというのは既にお伝えした通りです。
ただ、購入先の違いは値段だけではなく、「実物を見てすぐ買いたいか」 と 「比較して納得してから買いたいか」 のニーズにも影響します。
購入先は大きく「実店舗」と「オンラインストア」の2つのカテゴリーに分けられます。
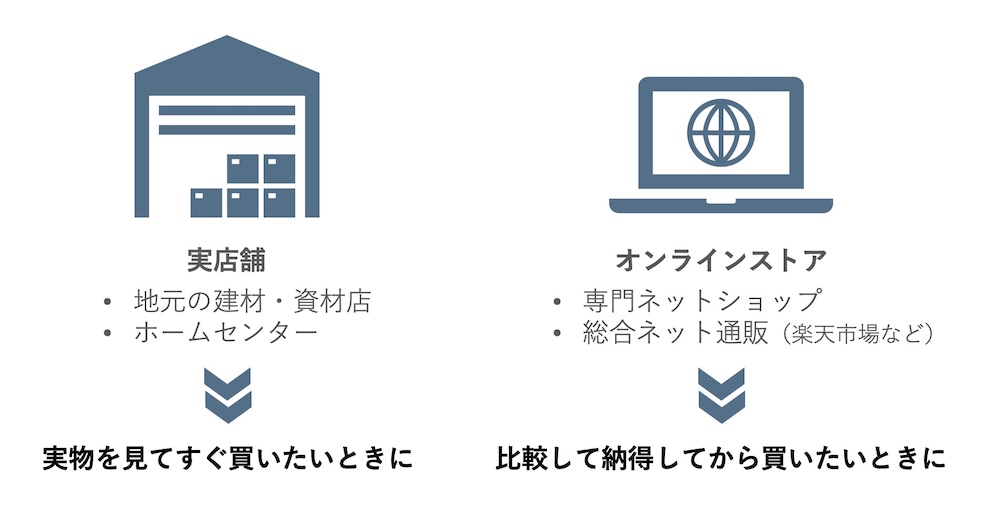
各購入先の特徴や向き・不向きについて、以下でもう少し詳しく見ていきましょう。
6-1. 【実店舗】地元の建材・資材店/ホームセンター
「その場で実物を確認して、そのまま持ち帰りたい」「すぐに必要」という場合、地元の建材・資材店とホームセンターといった実店舗は頼りになる選択肢です。
地元の建材・資材店は、建築関係者や設備関係者への販売に特化しているだけに、プロ向けの品揃えが充実しています。
一方、一般ユーザーも気軽に立ち寄れるホームセンターは、標準仕様中心ですが、アクセスが良く「緊急の買い足し」に対応しやすいです。
「すぐ使いたいシーン」では実店舗が有力な選択肢。
用途に応じて、専門性を求めるなら建材・資材店、ちょっとした買い足しならホームセンターと使い分けましょう。
6-2. 【オンライン】専門ネットショップ/総合ネット通販(楽天市場、Amazon等)
オンライン購入は、豊富な選択肢を検討した上で、納得してから買いたい場合に最適な方法です。
専門ネットショップは、商品ラインナップの幅広さが特徴です。
総合ネット通販(楽天市場、Amazon等)は、プロ向け商品のバリエーションこそ専門ネットショップに劣りますが、価格比較がしやすく、レビューも参考にでき、手軽に買える環境が整っています。
仕様や機能にこだわるなら専門ネットショップ、複数ショップの価格を横断的に比較したいなら総合ネット通販がおすすめです。
オンライン購入は、今すぐ手に入れたいという場合には向きませんが、「じっくり選びたい」「効率的に買いたい」というニーズに応える頼もしい選択肢です。
| 足場JAPANならメッシュシートをお得に購入可能! |
|---|
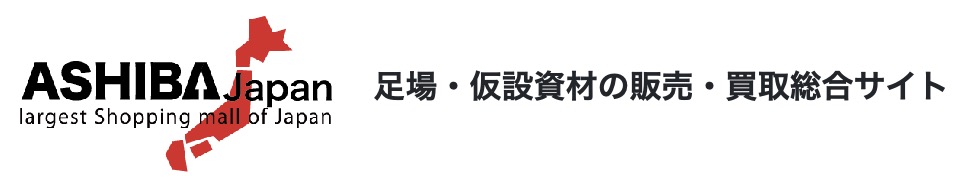 足場・仮設資材の販売・買取総合サイト「足場JAPAN」では、豊富なラインナップの足場材の他に、メッシュシートも販売しています。 大規模工事も事業として行なっている会社が運営しており、販売分と自社使用分をまとめて仕入れるため、スケールメリットでリーズナブルにご提供可能です。 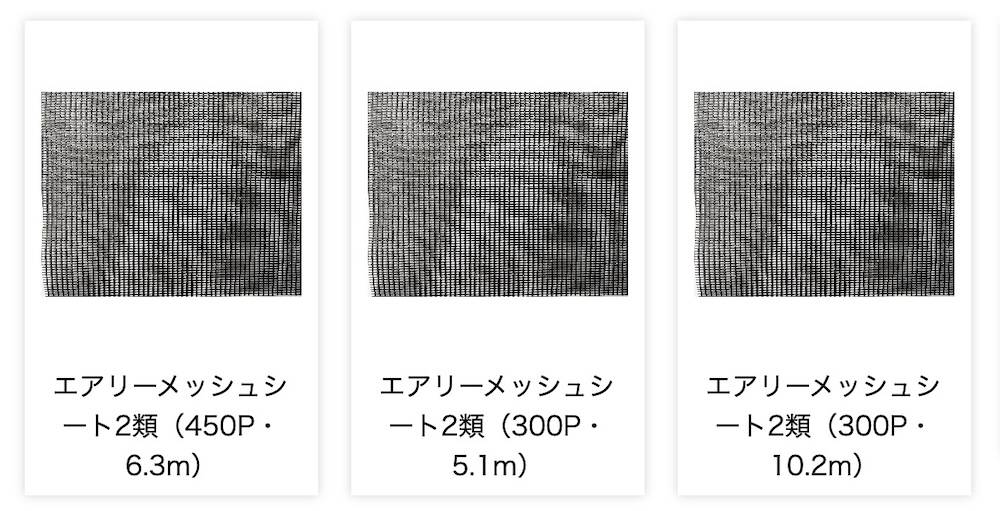 エアリーメッシュシート2類各種|足場JAPAN メッシュシートだけでなく、その他の資材も豊富に取り揃えています。 まとまったご注文に対しては、価格調整にも柔軟に対応させていただきます。 販売だけでなくレンタルも行っていますので、メッシュシートは「購入するほどではない」「使用後の洗濯が面倒」といった場合にも、ぜひご利用ください。 また、最短ルートでの発送を目指した全国5拠点体制で、在庫さえあれば即日発送も可能。 資材センターでのお引き取りもお選びいただけます。 納期・在庫等、オンラインストアに掲載されていない商品含め、まずはお気軽にお問合せください。 |
7. まとめ
メッシュシートの基本情報やおすすめ仕様についてお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。
▼メッシュシートとは、足場に張る網目状のシートのこと。
▼足場に張るメッシュシートの主な役割は、下記の2つ。
- 落下物による災害防止
- 塗料・洗浄水などの飛散防止
さらに、副次的な効果として、次の3つも挙げられる。
- 現場内部の様子を外部から見えにくくする
- 強い陽射しや風を遮る
- 作業員墜落時に一気に地上まで落下するのを防ぐ
▼法令で定められている危険防止措置の手段はメッシュシートに限られない。
しかし、メッシュシートは手軽で利便性が高いため、現場における事実上のスタンダードとなっている。
▼足場用メッシュシートのメリットは下表の通り。
| 足場用メッシュシートのメリット4つ |
|---|
|
▼足場用メッシュシートの使用における注意点は下表の通り。
| 足場用メッシュシートの使用における注意点 |
|---|
|
▼総合的に見ておすすめのメッシュシートは、下表のようなスペックのもの。
| メッシュシートのおすすめ仕様 | |
|---|---|
| 分類 | 2類 |
| サイズ | 1.8m幅 |
| 目合い | 1〜2mm程度 |
| 色 | 黒 |
▼メッシュシートを購入する場合とレンタルする場合それぞれのおおよその価格相場は下表の通り。
| メッシュシートの価格相場 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 購入する場合の価格相場 | レンタルする場合の価格相場 |
| 1類 | 8,000〜20,000円/枚 | 1日当たり数百円/枚 |
| 2類 | 2,000〜5,000円/枚 | |
▼メッシュシートの購入先は下図の通り。
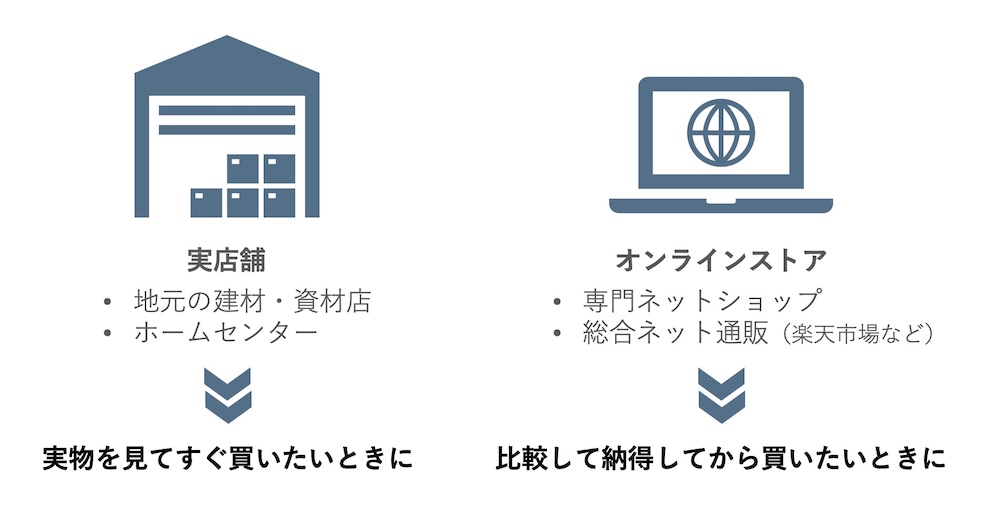
メッシュシートの選び方ひとつで、現場の印象も、仕事の質も変わります。
本記事が、貴社に最適なメッシュシート選びの一助となりましたら幸いです。
▼合わせてこちらもご覧ください▼
足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説
足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介














コメント