「足場屋と鳶職の違いってなんだろう」
「足場屋という仕事について詳しく知りたい」
足場屋という言葉は聞いたことあるし、仕事内容や働き方について気になるけど、
・仕事内容はどんな感じなのか
・未経験からでもチャレンジできる仕事なのか
・鳶職と足場屋はどう違うのか
といった点について、実際のところはどうなのか?は気になりますよね。
そこで本記事では、足場の施工や販売を手掛ける専門家である株式会社エルラインが、足場屋の基本的な仕事内容やきついポイント、足場屋と鳶職との違い、向いている人の特徴から給料事情まで詳しく解説していきます。
数多くの職人を抱えるエルラインだからこそ話せるリアルな事情を説明していくので、最後までご覧ください。
足場屋とは?仕事内容について解説

足場屋とは、一言でいうと「建設現場で足場を組み上げる職人さんのこと」です。
例えば、5階建ての新築マンションを施工する時について考えてみましょう。何もない土地に5階建ての建物を建てる訳ですので、5階で職人さんが作業できるように仮設足場を構築する必要があります。この仮設足場を構築するのが足場屋の仕事です。
建物を作るためには鉄筋を配置していったり、コンクリートが入る型枠を施工したり、電気を使えるようにするために電気工事をしたりする必要があります。
様々な職人さんが建物内で作業しますが施工前は階段がありません。何もしなければ施工場所へとたどり着くことはできません。そこで、仮設足場を構築することでやっと、他の職人さんが現場で作業をすることができるのです。
足場屋の具体的な仕事内容としては、下記の様なものが挙げられます。
・足場材を現場に搬入する
・搬入した足場材を現場に仮置きする
・図面通りに足場を組み上げる
・使用している足場の管理をする
・使い終わった足場を解体する
・解体した足場を現場の外に搬出する
足場を搬入し、組み上げ、使用中の管理をして、使い終わったら解体して、現場の外へと搬出する。この一連の流れが足場屋の仕事内容です。
より具体的な仕事の流れ、一日の流れについては下記記事を参考にしてください。
参考:鳶職(とび職)とは?仕事内容からリアル年収まで足場会社が徹底解説
また、株式会社エルラインではYouTubeで足場を組立てている様子を公開しています。勉強にもなりますし、実際に足場を組立てるイメージも掴めると思うので、是非見てみてください。
足場屋と鳶職の違いは?
足場屋に違い言葉として「鳶職」と呼ばれるものがあります。足場屋と鳶職を混同している場合があるので、2つの違いについて理解しておきましょう。
先ほどもお伝えした通り、足場屋の仕事は「足場を組み上げること」です。一方で、鳶職の仕事内容は「足場の組立て、鉄骨の組立て、重量物の楊重と据え付け」です。それぞれが足場鳶・鉄骨鳶・重量鳶と呼ばれています。
・足場鳶:建設現場で仮設足場を組み上げる
・鉄骨鳶:鉄骨造の現場で鉄骨を組立てる(現場では建方といいます)
・重量鳶:大型の機械や設備といった重量物を、運搬し、設置・解体する
足場鳶・鉄骨鳶・重量鳶のことを総称して「鳶職」と呼びます。
つまり、足場屋と鳶職の違いは「足場だけやるか?鉄骨や重量物も対応するか?の違い」です。
足場屋は足場を組み上げる「足場鳶」としての仕事に限定される一方で、鳶職は足場鳶だけでなく、鉄骨鳶や重量鳶としての仕事も内包されます。鳶職の方が業務のカバー領域が広いです。
弊社の鳶職人にも足場屋と鳶職の違いについてインタビューしている様子をTikTokにアップロードしてありますので、現場で働く生の声をみてみてください。
「足場屋」という言葉や「鳶職」という言葉は、実際の現場で働く人からすると微妙にニュアンスが異なります。動画の通り、人によっては「そもそも足場職人と言われるのが嫌い」という人もいるので、現場に行った際の呼び方には注意が必要です。
また、筆者も現場で働いていた経験からお伝えするのですが、「足場屋」や「鳶職」といった言葉をそこまで区別して言葉を使っていない人もいます。今回ご紹介したのは、あくまで定義のお話ですので、ご認識いただければと思います。
足場屋の仕事って危険?安全に働けるの?
人によっては、足場屋の仕事が危険であるというイメージを持っている方もいると思います。同時に「足場屋になったときに、安全に働けるのだろうか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。その疑問に対する回答をお伝えします。
確かに足場屋の仕事は危険ですが、やるべきことをしっかりやれば安全に働くことができます。
危険な理由としては、そもそも建設現場自体に危険が潜んでいるということも挙げられますが、足場屋に限定して言うと高所での作業が多いのも理由の一つです。

街中を歩くと、この様に背丈の高い足場が組んであるのを見ることもあると思います。足場屋として働くとなると、同じものを施工しなければならない。つまりは、この高さで作業をしなければならないから危険であるということです。
ただ、現場では安全帯の着用が義務付けられており、適切な安全設備の中で作業する分には安全です。
手すりに安全帯のフックをかけることで、墜落災害の防止をすることができます。実際に建設現場で墜落災害は数多く起こっていますが、その要因のほとんどが「フックを手すりにかけていないこと」です。
実際に働く職人さんの一部では、こういった安全設備を使うことを面倒と感じる人が多いです。面倒くさがって省略することが原因で事故が起こってしまいます。
逆をいうと、安全に働くことを面倒くさがらず、やるべきことをキッチリやれば、足場屋としてかなり安全に働くことができます。
また、現場での災害は他にも「熱中症」だったり、「感電災害」であったり、「飛来・落下事故」などがありますが、それらも同様に、やるべきことをしっかりとやっていれば事故の確率を大きく下げることができます。
足場屋のやりがい
ここまで足場屋としての仕事内容や働き方について触れてきましたが、足場屋として働いた時のやりがいについてもお伝えできればと思います。
他の仕事にはないやりがいがありますので、生の声を聴いていただければと思います。
足場屋のやりがい①地図に残る仕事をすることができる
足場屋の仕事は、建物が完成すると姿を消しますが、その建物は「地図に残る」存在となります。
自分が組んだ足場の上で、多くの職人さんが安全に作業を進め、やがて立派な建物が完成した時の達成感は、何物にも代えがたいものです。
「あの建物の足場は俺たちが組んだんだ!」と誇りを持って言える瞬間は、足場屋ならではの大きなやりがいです。特に、ランドマークとなるような大きな建物や、地域の誰もが知る施設の建設に携われた時の喜びはひとしおでしょう。
足場屋のやりがい②チームで一つのことをやりきる達成感
足場組立は、一人では決してできない仕事です。高所での作業では、声を掛け合い、互いの動きを予測し、完璧な連携が求められます。
危険と隣り合わせの状況だからこそ、仲間との信頼関係は何よりも重要。「命綱」とも言える絆が育まれます。難しい現場をチーム全員で乗り越え、無事に足場が完成した時の達成感は、まさにスポーツのチームプレイにも似た一体感があります。この「仲間と成し遂げた」という感覚は、足場屋の大きなやりがいの一つです。
足場屋のやりがい③高収入を狙うことができる
足場屋の仕事は肉体的にきつい側面もありますが、その分、比較的高い収入を得られる可能性があります。
特に経験を積み、資格を取得していくことで、日給や月給が上がっていくのが現実です。自分の努力とスキルアップが、収入という形で明確に評価されることは、大きなやりがいにつながります。
家族を支えたり、自分の夢を叶えたりするために、頑張りが直接的な報酬に結びつく点は、足場屋として働く大きな魅力の一つと言えるでしょう。
足場屋のやりがい④社会のインフラを支える重要な役割を果たせる
建物が建つ場所、人が住む場所、働く場所、生活を支えるインフラの整備など、足場がなければ始まらない工事は星の数ほどあります。
足場屋は、安全な作業環境を提供することで、日本の建設業、ひいては社会全体の発展を根底から支えています。自分たちの仕事が、人々の暮らしや経済活動を陰で支えているという貢献を実感できることは、大きなモチベーションとなるでしょう。社会に必要とされているという実感は、足場屋の仕事に深みを与えます。
足場屋のやりがい⑤毎日色んなことが起こるので飽きない
足場屋の仕事は、同じ現場が二つとありません。住宅、マンション、商業施設、工場、橋梁、イベント会場など、それぞれの現場で建物の形や立地条件が異なり、求められる足場の種類や組み方も変わってきます。
毎回新しい課題に直面し、それを解決していく過程で、図面を読む力、現場での判断力、そして応用力が自然と養われます。同じことの繰り返しではないため、飽きがくることがなく、常に新しい知識や技術を習得し、自分自身が成長していくことを実感できるでしょう。
足場屋として働く上できついポイント

足場屋にはやりがいもありますが、働いていてきついポイントもあります。足場屋として働く前に「どんなところがきついのか?」といったポイントについて理解しておきましょう。
足場屋がきついポイント①資材の運搬や足場の組立て等が体力的にきつい
足場材は一本一本が重く、長いものも多いため、現場での運搬や荷揚げ、荷降ろしは大変です。特に階段での運搬や、足元が悪い場所での作業は、全身の筋肉を使うため、常に高い体力レベルが求められます。
朝から晩まで体を動かすため、一日が終わる頃には疲労困憊になることも珍しくありません。
足場屋がきついポイント②高所など不安定な足場の上で作業する必要がある
足場屋の仕事は、まさに「足場の上で足場を組む」作業の連続です。まだ不安定な状態の足場の上や、狭い場所でバランスを取りながら作業を進める必要があります。
慣れるまでは高所への恐怖心も伴い、常に集中力と慎重さが求められるため、精神的なプレッシャーも大きいです。
足場屋がきついポイント③夜勤で現場に入ることもあるところ
商業施設や公共施設など、日中の作業が難しい現場では、夜間や早朝に足場の組み立てや解体を行うことがあります。
生活リズムが不規則になりやすく、体調管理が難しくなるのがこの点のきつさです。夜間の作業は視界も悪くなるため、日中以上に集中力と安全意識が求められます。
足場屋がきついポイント④炎天下の仕事では熱中症のリスクがある
夏場の建設現場は、日差しを遮るものが少なく、直射日光を浴びながらの作業が続きます。
足場材が熱を持つこともあり、体感温度はさらに上昇します。大量の汗をかき、こまめな水分補給が欠かせませんが、それでも熱中症のリスクは高く、体力的にも精神的にも非常に過酷な環境となります。
足場屋がきついポイント⑤専門用語と覚えることが多い
足場の種類や部材の名前、組み立ての手順、安全に関する規定など、足場屋には覚えるべき専門用語やルールが非常に多いです。特に未経験から始める場合、最初は戸惑うことも多いでしょう。
覚えることが多いだけでなく、それを実際の作業で正確に使いこなす必要があるため、常に学び続ける姿勢が求められます。
以上が足場屋として働いたときにきついと感じるポイントです。
足場屋の年収・給料事情は?

次に足場屋の年収・給料事情についてお伝えしていきます。前提として足場屋の年収や給料はその人の経験や能力によって異なります。
まずは未経験者として現場に入り、最初は先輩の補佐として働いていきます。ある程度一人で仕事を回せるようになったら、中堅職人として徐々に責任ある仕事を任されるようになります。
現場のリーダー(職長)になったら現場全体を統括することになり、そこから更に上へといくと、自分の会社を作って独立したり、会社の中核を担う存在になっていきます。
それぞれのフェーズにおける年収・給料の目安は下記です。
| 経験 | 仕事内容 | 月収目安 | 年収目安 |
| 未経験者(0〜3年) | 基本的な作業 | 20万円〜25万円 | 約250万円〜300万円 |
| 中堅職人(3〜7年) | より責任ある仕事を任されるようになる | 30万円〜40万円 | 約400万円〜500万円 |
| 職長(7〜10年) | 現場全体の管理や作業員の教育など | 40万円〜50万円 | 約500万円〜600万円 |
| 独立・自営(10年〜) | 自分の会社を立ち上げたり、会社経営 | 50万円〜100万円以上 | 約600万円〜1000万円以上 |
人によっては目安よりも早いタイミングで昇格することもありますし、人によっては遅いタイミングでの昇格になることもあります。独立・自営に関しては個人の能力も問われるため、そこまでいかない人も一定数いるでしょう。
現場で働いて実務経験を積んだり、勉強して現場で必要な知識を身に着けることも大事ですが、足場屋としてキャリアアップするためには資格取得も必要です。
現場の実務経験と資格取得を両軸で進めることで、自分の給料をあげていくことができます。
下記の動画では、エルラインのベテラン職人にインタビューをしており、その中で給料事情について触れています。是非参考にしてください。
足場屋に必要な資格
足場屋の資格は「必須の資格」と「必須ではないがキャリアアップに繋がる資格」がありますので、それぞれに分けて解説していきます。
必須の資格
まず必須の資格としては「足場の組立て等特別教育」が挙げられます。
足場の組立て・解体・変更の作業に従事する場合はこの資格が必要です。資格取得には1日講座を受講する必要があるので、足場屋として就業する場合は必ず受講しましょう。
| 特別教育とは? |
|---|
| 労働安全衛生法に基づいて、事業者が危険または有害な業務に労働者を就かせるときに、その業務に関する安全または衛生のための特別な教育を行うこと。 |
必須ではないがキャリアアップに繋がる資格
また、必須ではないが取得すると役立つ資格としては、下記の様な資格が挙げられます。
・足場の組立て等作業主任者
・とび技能士
・玉掛け技能講習
・高所作業車運転技能講習
・フォークリフト運転技能講習
足場の組立て等作業主任者(技能講習)
概要: つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張り出し足場、または高さ5メートル以上の構造の足場の組立て、解体、変更の作業において、作業の指揮・監督を行うための資格です。
対象:
- 足場の組立て、解体または変更に関する作業に3年以上従事した経験があり、満21歳以上の者。
- 土木、建築、造船に関する学科を専攻して卒業後、2年以上足場の組立て、解体または変更に関する作業に従事した経験がある者。
講習時間: 学科13時間
役割: 足場の材料の点検、不良品の排除、作業手順の指示、安全帯などの保護具の使用状況の確認など、現場の安全管理全般を担います。足場作業における責任者となる資格です。
とび技能士(国家資格)
概要: とび工事の施工に必要な技能・知識を認定する国家資格です。1級、2級、3級の3段階があります。
等級:
- 3級: 初級者向け。年齢・学歴に関係なく受験可能。
- 2級: 中級者向け。2年以上の実務経験、または3級合格者。
- 1級: 上級者向け。7年以上の実務経験(2級合格者は2年、3級合格者は4年の実務経験が必要)。
試験内容: 学科試験と実技試験があります。実技試験では、足場の組立てや解体などのとび作業の実技が問われます。
目的: とび職としての高い技能と知識を証明し、キャリアアップや独立にも有利になります。
玉掛け技能講習
クレーン等で荷物を吊り上げる際に、フックにワイヤーロープなどを掛ける作業(玉掛け)を行うための資格。足場材の荷揚げなどに必要となる場合があります。
高所作業車運転技能講習
作業床の高さが10m以上の高所作業車を運転するための資格。足場を組むのが難しい場所での作業や、点検作業などで使用する可能性があります。
フォークリフト運転技能講習
最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転するための資格。資材置き場などで足場材を運搬する際に役立ちます。
足場屋は未経験からでも挑戦できる?

足場屋は未経験からでも挑戦することができます。
実際に弊社でも未経験から足場屋として活躍している職人さんは数多く在籍しています。
もちろん、最初は覚えることがたくさんあります。足場には様々種類がありますので、それぞれの名前や組み上げ方を覚えていく必要があります。例えば、下記の様な種類の足場があります。
※クリックすると各足場の解説記事へ飛ぶよう設定しているので、よろしければご覧ください。
・単管足場
・枠組足場
・次世代足場
・くさび緊結式足場
・ステージ足場
・本足場
・棚足場
・移動式足場
・手摺先行足場
・ダーウィン足場
上記で挙げた足場はあくまで一例です。また、それぞれも細かい部材の集合体となっているので、部材の名前を覚えたり、組み上げの流れを覚えたり、自分がどう動けばいいのか?を学ぶ必要があります。また、基本的に建設現場で働くので、現場の基本的なルールについても学んでいく必要があります。
ただ、それらは現場で働く足場屋さん全員が通る道なので、一つ一つを学んでいけば問題ありません。むしろ、学ぶことが多いからこそ、専門性の高い職業として安定して長く働き続けられます。
下記動画は実際に現場で働く社員のインタビューでどんな人を採用したいか?といった趣旨の動画です。
どんな人が向いているのか?といったところが掴めると思いますので、是非ご覧ください。
足場屋に向いている人
それでは改めて、どんな人が足場屋に向いているのでしょうか?といったところについて伝えていきます。
足場屋に向いている人①手に職をつけたいと考えている人
足場工事は高度な専門技術を要する職業であり、一度身につけた技術は一生の財産となります。足場の組み立てや解体には、建物の構造を理解し、安全性を確保しながら効率的に作業を進める専門知識が必要です。
足場技能士などの国家資格を取得することで、技術力の証明となり、キャリアアップにもつながります。また、現場での経験を積むことで、様々な建物や工事現場に対応できる応用力も身につきます。技術職として長期的に安定した収入を得られるため、手に職をつけたい人には最適な職業といえるでしょう。
足場屋に向いている人②デスクワークより体を動かしたい人
足場工事は屋外での肉体労働が中心となるため、デスクワークが苦手で体を動かすことを好む人には理想的な職業です。毎日異なる現場で作業することで、単調な繰り返し作業から解放され、常に新鮮な気持ちで仕事に取り組めます。
適度な運動効果も期待でき、自然と体力や筋力が向上します。また、チームワークを重視する作業が多いため、同僚との連携を通じて達成感を共有できる点も魅力です。体力に自信がある人や、運動が好きな人にとっては、健康維持とキャリア形成を両立できる職種です。
足場屋に向いている人③形に残る仕事に誇りを持てる人
足場工事は建設プロジェクトの基盤となる重要な工程であり、自分が携わった建物が完成した時の達成感は格別です。マンション、オフィスビル、商業施設など、様々な建物の建設に関わることで、街づくりに貢献している実感を得られます。
完成した建物を見上げた時に「この建物の建設に自分も関わった」という誇りを感じられることは、足場工事の大きなやりがいの一つです。また、安全で確実な足場を提供することで、他の職人たちが安心して作業できる環境を作り出すという、縁の下の力持ち的な役割にも意義を見出せる人に向いています。
足場屋に向いている人④学歴や経歴に関係なく稼ぎたい人
足場工事業界では、学歴や職歴よりも技術力と経験が重視されるため、様々な背景を持つ人がチャンスを掴めます。未経験からスタートしても、努力次第で短期間で技術を身につけ、収入アップを実現できます。
技能士資格の取得や現場での実績を積むことで、親方として独立開業する道も開かれています。また、危険手当や高所作業手当などの特別手当により、一般的な職種よりも高い収入を得られる可能性があります。年功序列ではなく実力主義の側面が強いため、向上心のある人には大きなチャンスがある職業です。
足場屋に向いている人⑤かっこよく働きたい人
足場工事は高所での作業が多く、スピード感と正確性が求められる職人技の世界です。熟練した足場職人の手際よい作業は、まさに職人芸として多くの人から尊敬される技術です。
作業着やヘルメット、安全帯などの装備を身につけて高所で作業する姿は、建設現場のヒーローとしての格好良さがあります。また、チームワークを活かした連携作業や、限られた時間内で安全かつ効率的に作業を完了させる技術力は、周囲からの信頼と評価を得られます。職人としてのプライドを持ち、格好良く働きたい人にとって、足場工事は理想的な職業の一つといえるでしょう。
足場工事は建設業界において不可欠な職種であり、上記の特徴を持つ人々が活躍できる魅力的な職業です。安全第一を心がけながら、技術向上に努めることで、長期的なキャリア形成が可能な職種として注目されています。
株式会社エルラインは鳶職を採用しています
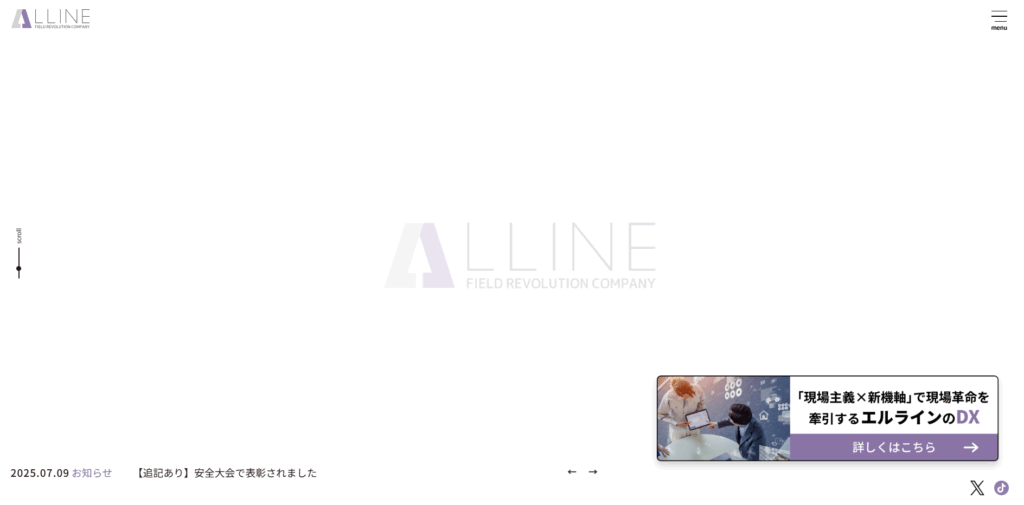
株式会社エルラインでは、未経験から一人前の鳶職に成長する環境が整っています。
常に数多くの現場が走っているので、実務経験として多様なスキルを身に着けることが可能です。まずは先輩社員の補助として働いていき、徐々に徐々に仕事に慣れて頂きます。
また、エルラインには技術継承を目的としたエルラインアカデミーという教育制度があります。アカデミーを通じてエルライングループに蓄積される技術を学ぶことができ、職人としてのキャリアアップも支援しています。
「まだ足場屋になることを決めていない」
「転職するかどうかもまだ悩んでいる」
そんな方でもOKです。足場屋としての第一歩を踏み出そうか悩んでいる人は是非、下のお問い合わせフォームからご連絡ください。
お待ちしております。














コメント