「塗装工ってどんな仕事なんだろう、、、」
「自分には向いているんだろうか、、、」
塗装工という仕事は知っているし、興味はあるけど、
・実際はどんな仕事か
・未経験からでもできるのか
・仕事をする上でどこが大変なのか
・一人立ちするにはどれくらいかかるのか
・収入はどれくらいか
・どんな資格があるのか
といった点に疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、塗装工事の専門家である日成工業株式会社を傘下に持つ株式会社エルラインが、塗装工の仕事内容や向いている人の特徴、年収や資格、キャリアパス等について解説していきます。
エルライングループとして、たくさんの塗装職人を抱えているからこそ話せる内部情報も合わせてお伝えしていくので、最後までご覧ください。
塗装工とは?仕事内容について解説する

塗装工とは、結論「建築物や構造物、橋梁、プラント(工場)などに塗装作業を施す専門職のこと」です。
建築物の例をイメージしてみましょう。建物は使えば使うほど劣化します。それは設備もそうですし、見た目的な部分もです。劣化した部分に対して、綺麗に塗料を塗ることで見た目は改善しますよね?これが塗装工の仕事の一例です。
塗装の目的には、美観の向上だけでなく、耐候性・防錆性能の向上、建物の寿命延長など多岐にわたる要素が含まれます。つまり、塗装工の仕事は単なる「塗る作業」ではなく、建物の性能や安全性を維持・向上させるための重要な業務です。
作業対象となる建物は、戸建住宅、マンション、ビル、工場、橋、高速道路の高架橋などさまざまで、現場によって必要な知識や技能が大きく異なります。また、塗装に使われる塗料の種類も豊富で、屋外用の耐候性に優れた塗料や、防水・防カビの性能を持った塗料、内装用の自然塗料など多岐にわたります。そのため、塗装工として働くには、材料や施工手法に関する専門知識も求められます。
以下に、塗装工の仕事内容として代表的な業務を表にまとめました。
| 業務内容 | 詳細 |
|---|---|
| 下地処理 | 塗装前に表面の汚れや古い塗膜、ひび割れなどを除去し、塗料がしっかり密着するよう下準備を行う |
| 養生 | 塗装しない箇所にビニールシートやマスキングテープでカバーを施し、塗料の飛散を防ぐ |
| 塗料の調合 | 場所や素材、気候条件などに応じて適切な塗料を選び、必要に応じて希釈や混合を行う |
| 塗装作業 | ハケ、ローラー、スプレーガンなどを用いて実際に塗装を行う |
| 乾燥・重ね塗り | 塗料の乾燥を確認し、複数層にわたって塗装することで耐久性や美観を高める |
| 完了検査 | 仕上がりを点検し、むらや塗り残しがないか確認し修正する |
| 清掃・片付け | 使用した用具や周辺の清掃、道具のメンテナンス、撤収作業などを行う |
塗装工の仕事には、体力を要する場面や厳しい気象条件下での作業も含まれ、夏の高温・冬の寒冷地での施工もあります。その中でも高所作業や足場上での作業が発生する現場もあるため、安全に対する高い意識が必要です。
塗料の種類によっては危険なものもあります。塗料に含まれる有機溶剤を吸い込むことで健康被害(頭痛やめまいなど)があったり、引火性のある塗料が原因で火災になる可能性もあります。
労働災害につながらないように換気を徹底したり、適切な保護具の着用が必要です。
また、高品質な仕上がりを実現するためには、色彩の知識や材料の扱いに関する熟練した技術力が必要です。ただ塗料を塗るだけではありません。
塗装技能士資格(厚生労働省)などの国家資格取得を目指す人も増えており、技術職としてのキャリア形成も可能です。
こうした背景のもと、塗装工は単なる「現場作業員」ではなく、意匠・技術・安全が求められる専門職となっています。建築・リフォーム業界において今後も欠かせない人材であり、将来性にも優れた職種の一つとされています。
塗装工の役割

建物の見た目を美しくする
塗装工の役割の一つ目は、建物や構造物の外観を整え、美しく保つことです。
経年劣化や汚れ、退色、ひび割れなどで悪化した外観を、熟練の技術と色彩感覚を活かして、新築同様の見栄えに回復させることが可能です。また、公共施設や商業施設、住宅など、それぞれの用途に応じた色彩設計を施すことで、景観や印象づくりにも貢献します。
例えば、住宅の外壁塗装では、近隣の建物との調和や、依頼主の好みに応じたカラーリングを行い、住まいとしての魅力を向上させます。商業施設では、集客力向上のためのデザイン性が重要視されることもあり、色彩設計はビジネスの一助ともなります。
安全性の向上
外観の美化だけでなく、塗装工は建物の構造の劣化を防ぎ、安全性を高める役割も担っています。特に日本のような高温多湿な気候では、外壁や鉄部、木部などが雨風、紫外線、湿気にさらされ、腐食やカビ、錆などが発生しやすくなります。それらを防ぐために、防水塗料や防錆塗料、遮熱塗料などの適切な塗料を選定し施工することが必要です。
特に鉄骨造の建築物においては、錆の進行が構造に深刻なダメージを与える可能性があるため、防錆塗装は極めて重要です。また、学校や病院などの公共施設では、安全基準を満たした塗料を使用し、環境安全性にも配慮する必要があります。
なお、防火・耐火塗料を施すことで、万が一の火災時に延焼を防ぎ、安全性を高める取り組みもあります。このように塗装は、美観だけでなく、安全性、機能性を担保する重要な要素なのです。
古くなった建物の修繕
塗装工は建物の維持管理や延命にも深く関わっています。年月の経過と共に外壁や屋根にはひび割れや剥がれなどの劣化が見られるようになります。そのまま放置してしまうと、雨水などが建物内部に侵入し構造材を腐敗させる恐れがあります。塗装はこのような劣化を未然に防ぎ、建物全体の寿命を延ばすための補修作業として欠かせません。
実際の修繕工程では、塗装工がクラック(ひび割れ)処理や洗浄、下地調整を行った後、適切な下塗り、中塗り、上塗りの工程を遵守することで、美観と機能性を両立した仕上がりを実現します。
また、多くのマンションや公共施設では定期的な大規模修繕計画が立てられており、塗装工はそうしたプロジェクトの中で専門技術者としての役割を果たします。これは、建築基準や検査基準を満たす施工精度が塗装工に求められることを意味します。
塗装工の一日の流れは?
塗装工の一日の流れは、おおむね下記のような流れで進行します。前提として、会社や現場によっても異なりますし、同じ現場でも工期によって働く時間は変わったりします。
ここでは割愛しますが、10:00~10:30と15:00~15:30あたりの時間帯で一服を取る現場が多い印象です。
| 時間帯 | 主な作業内容 |
|---|---|
| 7:45〜8:15 | 集合・朝礼・KY活動(危険予知活動) |
| 8:15〜8:45 | 作業準備(養生、機材の準備など) |
| 8:45〜12:00 | 塗装作業 |
| 12:00〜13:00 | 昼休憩 |
| 13:00〜15:15 | 塗装の続き |
| 15:15〜16:30 | 仕上げ・点検・清掃・片付け |
| 16:30〜17:00 | 記録と報告、次の日の予定確認、解散 |
1.集合・朝礼・KY活動(7:45~8:15)
朝礼の時間は現場によって変わりますが、新築工事の場合は8時のところが多いです。
8時に朝礼が開始ですので、7:45には現場に到着します。朝礼前に施工管理の人や職長の人達と本日の作業内容についてあらかじめ打ち合わせをしておきます。
朝礼ではKY活動(危険予知活動)を行います。KY活動では、その日の作業において考えられる事故や怪我のリスクを洗い出し、安全に作業するための行動確認が必要です。その際、全員で当日のスケジュール、使用する材料、作業エリア、他業種との兼ね合い、有機溶剤や足場の注意点などを共有します。
現場全体での朝礼が終わった後に作業場所へ向かい、作業場所でも改めてKY活動をします。
2.作業準備(養生、機材の準備など)(8:15~8:45)
KY活動が終わったら、塗装に必要な材料や工具、足場、安全装備の確認を行い、養生作業などの準備を進めます。
養生は、塗料が付着してはいけない箇所(ガラス、金属部材、サッシ周りなど)にマスキングテープやビニールシートで覆いをかける作業です。ここでの準備の精度が、仕上がりの美しさにも大きく影響します。
3.塗装作業(8:45~12:00)
塗装作業の準備が終わったら実際に塗装作業を行っていきます。
下塗り、中塗り、上塗りの3工程で塗装を行うのが基本です。最初にプライマーやシーラーといった下塗り剤を使い、素材と塗料の密着性を高めます。
次に主材となる塗料で中塗り、さらに同じ塗料で上塗りを行って美観と機能性(防水性、耐久性など)を完成させていきます。ローラー、刷毛、スプレーガンなどを適切に使い分ける技術が求められます。
4.昼食と休憩(12:00~13:00)
12時になったらお昼休憩を1時間取ります。
特に夏場は熱中症対策も必要で、適度な水分補給と塩分補給が大事です。しっかりとご飯を食べることで栄養を補給し、体を休めることで体力回復をします。
集中力の低下は労働災害を引き起こす原因になるので、しっかりと休憩を取ります。
5.塗装の続き(13:00~15:15)
午後からは、午前中の続きを行うか、乾いた部分を確認して次の塗装工程に進みます。
場合によっては補修や重ね塗りを行い、均一で美しい仕上がりを目指します。天候に左右される仕事であるため、進行具合は臨機応変に調整されます。気温や湿度を考慮して塗料の乾燥時間も管理する必要があります。
6.仕上げ・点検・清掃(15:15~16:15)
すべての工程が終わった後は、細部の仕上げ作業や補修を行います。施工ミスや塗り残しがないかの点検を行い、不備があれば早急に修正対応します。
施工ミスや塗り残しの点検に関しては職人側で行うこともありますが、施工管理(現場監督)の人が行うことが多いです。施工図と現場の状況を比較し、必要があれば是正をしていきます。
7.片付け(16:15~16:30)
その日の作業が終わったら片付けを行います。現場では4S(整理・整頓・清潔・清掃)が大事です。
使用した機材や塗料を正しい方法で清掃・収納し、現場周辺を整理整頓します。廃材や塗料缶など産業廃棄物は分別処理が義務づけられており、マニュアルに則って処理する必要があります。片付けは事故防止にもつながる大切な作業です。
8.記録と報告、次の日の予定確認、解散(16:30~17:00)
作業終了後は「KY用紙」と呼ばれる報告書を記入して元請の会社に提出します。提出の際に施工管理に作業の進捗を報告し、次の日の予定を確認してから解散します。
次回の予定を確認するときには、
・いつまでにどこまでやらなけばいけないのか?
・工程に対して遅れはないか?
・次の作業を終わらせるには人員が何名必要なのか?
といったところを明確にすることが大事です。
塗装工の仕事をする上でつらいポイント

淡々と自分の仕事を進めていく必要がある
塗装工の仕事は一つひとつの作業が単調であっても、長時間集中して黙々と取り組む姿勢が求められます。とくに、広い外壁や天井の塗装などでは単純作業が多く、ルーチンワークの繰り返しになりがちです。そうした中でもミスは許されず、丁寧かつ均一な塗装が求められるため、精神的な持久力が必要です。
また、作業中は、一人で黙々と作業を続ける時間が長くなる傾向があります。チームで動いていても基本的には個人作業が中心で、自らの業務を自律的に遂行する力が求められます。
体調管理をしっかりしないといけない
塗装工の仕事は基本的に体力勝負です。
夏場の猛暑や冬場の寒冷な環境でも外で作業をするケースがあり、体力と健康の維持が重要です。とくに熱中症対策や水分補給、寒さ対策は欠かせません。健康管理が不十分だと作業効率が落ちるだけでなく、安全面にも悪影響を与えます。
現場へ行くと施工管理の方から下記のようなチェックをされます。
・しっかりと睡眠をとってきたか?
・朝食をとってきたか?
・二日酔いではないか?
・定期的に水分補給と塩分補給をしているか?
特に二日酔いの場合は体内の水分が不足し、熱中症になりやすい傾向があります。熱中症にならないように体調管理をする必要があります。
また、塗装工の仕事は自分の体が資本です。体調を崩して働けないとなると、給料に直結してしまいます。しっかりと働き続けられるように自分の体調管理をしっかりとする必要があります。
建設現場には危険がある(化学薬品等)
塗料やシンナーなど、有機溶剤を使用することが多いため、健康被害のリスクがあります。これらの薬品は長期間吸引すると中枢神経や呼吸器に悪影響を及ぼす恐れがあります。適切にマスクなどの保護具を着用し、換気を確保したうえで作業しなければなりません。
この辺りの安全管理については、現場全体および会社全体でも徹底しています。特に、大きな会社になればなるほど、大きな現場になればなるほど、厳格な管理が必要です。
職人さんによっては「めんどくさいから」という理由で安全管理をないがしろにする人もいます。
ただ、塗装工は使用するものが人体に危険を及ぼすことが多いので、作業環境管理をしっかりやらなければなりません。
また、足場や高所作業も多く、転落や工具の落下などの事故も発生しやすいため、常に高い安全意識と注意力が求められます。
現場のイレギュラーに巻き込まれることがある
建設現場では予定通りに作業が進まないことが多くあります。たとえば、天候の変化により塗装が中断されることや、他の職種の作業の遅れが原因で自分の作業に影響が及ぶことも珍しくありません。
また、建材の納入遅れや施主からの仕様変更など、突発的なトラブルへの対応が求められることもあり、常に柔軟な対応力が必要です。筆者も経験はありますが、この様なイレギュラーは精神的にも辛い部分があります。とはいえ、現場にはイレギュラーがつきものですので、こういった事態は想定しなければなりません。
様々な施工方法について学ぶ必要がある(単に色を塗るだけではない)
塗装工は単にペンキを塗るだけでなく、下地処理、防水処理、養生作業、仕上げ、検査といった多段階にわたる工程を理解し、適切に作業する必要があります。建物の素材や環境に応じて塗料の種類や施工方法も変わるため、多岐にわたる知識の習得が求められます。
さらに、建築基準法や施工マニュアル、安全衛生教育に基づいた判断が不可欠であり、現場経験と座学の両方からスキルを積み上げていく必要があります。
だからこそ、塗装工は専門性が高く価値の高い仕事であることも事実です。日々、現場で専門的な知識を学び続ける姿勢が必要になります。
塗装工の仕事をする上でつらいポイントのまとめ
塗装工の仕事をする上でつらいポイントを表にまとめました。
| つらいポイント | 詳細 |
|---|---|
| 淡々と仕事を進める必要がある | 長時間黙々と仕事をしていく必要がある |
| 体調管理をしっかりしないといけない | 体調を崩して現場に穴をあけないように、常日頃から体調を管理する必要がある |
| 現場の安全管理を徹底する必要がある | 保護具の着用や環境など、作業環境に注意して仕事をする必要がある |
| イレギュラー対応がある | 現場の都合によって作業時期が遅れたり、やり直しになったりすることもある |
| 施工方法を学ぶ必要がある | 様々な塗装の施工について学び続ける必要がある |
塗装工に向いている人は?

塗装工には向き・不向きがある仕事です。それでは、どのような人が塗装工に向いているのでしょうか?
塗装工に向いている人の特徴を下記7つにまとめました。
・細かい作業が得意な人
・体を動かすのが好きな人
・色彩感覚がある人
・協調性がある人
・安全意識が高い人
・ものずくりが好きな人
・心身ともにタフな人
細かい作業が得意な人
塗装作業は養生、下地処理、塗り重ねといった工程を経て、仕上げに至ることから、細部まで気を配る注意深さが求められます。小さなムラや塗り残しなども許されないため、細かい作業が得意な人は塗装工に向いています。手先の器用さや集中力の高さが活かせる仕事です。
向いている人の特徴
・手先が器用
・集中を継続できる
・慎重に作業するのが得意
体を動かすのが好きな人
塗装工は基本的に屋外作業であり、高所作業や長時間の立ち仕事もあります。そのため、体を動かすことが好きで、体力や持久力に自信がある人は向いているでしょう。
デスクワークよりも肉体的な仕事に魅力を感じるタイプに最適な業種です。
向いている人の特徴
・一日中座っているより動きたい
・学生時代に体育が好きだった
・肉体的な仕事に魅力を感じる
安全意識が高い人
高所作業や有機溶剤の使用といったリスクがあるため、安全意識の高さは必須です。作業前のKY活動(危険予知活動)や保護具の着用、ルールの徹底が求められる現場では、常にリスクに対して敏感でいられる人が活躍できます。
事故を未然に防ぐための意識が高い人にはぴったりの職種です。
向いている人の特徴
・事故を起こすのが怖いと感じる人
・安全管理をめんどくさがらずにやれる
ものづくりが好きな人
塗装工の仕事は、「色を塗る」という作業にとどまらず、人が使う建物を美しく・機能的に仕上げるクリエイティブなものづくりです。仕上げの良し悪しが目に見えて分かるため、作る楽しさを味わいたい人、職人として職に誇りを持ちたい人には最適です。
向いている人の特徴
・自分の仕事に誇りを持ちたい
・一つのものを作り上げるのが好き
・かっこいい仕事がしたい
心身ともにタフな人
塗装工は季節や天候に左右される仕事であり、夏の高温や冬の寒さの中でも作業が必要となることがあります。加えて、スケジュールの遅延により、納期に追われるプレッシャーがかかることもあります。
そうした中でも安定して自分の仕事をし続けられる人が向いています
向いている人の特徴
・体力に自信がある
・めんどうなことがあっても折れない
・体調管理ができる
塗装工に向いている人は?|まとめ
| 向いている人 | その理由 |
|---|---|
| 細かい作業が得意 | 養生、仕上げ作業などで正確さが求められる |
| 体を動かすのが好き | 屋外での長時間作業、高所作業に対応できる |
| 安全意識が高い | 高所作業や危険物の取り扱いを伴う |
| ものづくりが好き | 建物の仕上げを担当、完成時の達成感がある |
| 心身ともにタフ | 天候や納期による過酷な環境にも適応できる人 |
これらの特性は、塗装工という仕事を長く続けていくために非常に重要な資質です。未経験であっても、向いているタイプであれば着実に技術を身につけて一人前の職人になることが可能です。
塗装工の給与や年収は?

塗装工の年収は、経験年数や職位、スキルレベル、所属する会社の規模や地域性などに大きく左右されます。以下に、勤続年数別に塗装工の収入イメージをわかりやすくまとめました。
| キャリア段階 | 想定年収(目安) | 仕事内容の特徴 |
|---|---|---|
| 未経験者(0〜3年) | 250万円〜350万円 | 現場の補助作業。道具の準備や清掃、養生などが中心。先輩の指導を受けながら技術習得中。 |
| 中堅職人(3〜7年) | 350万円〜450万円 | 実際の塗装作業を担う中心メンバー。現場工程の把握や後輩指導も求められる。 |
| 職長(リーダー職)(7〜10年) | 450万円〜600万円 | 複数の現場を管理・指導するポジション。顧客との調整、工程管理、安全管理の責任が発生。 |
| 経営者・独立(10年〜) | 600万円〜1,000万円以上 | 自社の組織運営・経営を担い、案件の受注や顧客対応まで広範な業務を行う。 |
未経験者(0〜3年)
未経験から塗装工に挑戦する場合、最初は見習いとして現場に同行し、先輩職人のお手伝い・サポートから仕事を始めていきます。
先輩社員と一緒に仕事をすることで道具の名前や使い方、塗料の種類、作業手順を学びながら仕事を覚えていきます。この時期に基本的な知識を少しずつ身に着けていくことが大事です。
また、塗装工という専門性だけでなく、建設業界の全体に対する知識も学んでいくと良いでしょう。
具体的には、現場の流れ、工程、他業者との兼ね合い、安全管理、作業環境管理など、現場にいるだけで学べることは無数にあります。
年収の目安
・月収:20万円~30万円
・年収:約250万円~350万円
中堅職人(3〜7年)
ある程度の経験を積み、施工技術と現場対応力が身に付くと、中核人材として活躍するようになります。
一般住宅の外壁塗装や大型施設の内装塗装など、さまざまな現場を任されるようになり、技術力によって高単価の案件にも対応可能です。後から入ってきた後輩の育成であったり、現場全体の管理などを徐々に任されるようになります。
年収の目安
・月収:30万円~40万円
・年収:約350万円~500万円
職長(リーダー職)(7〜10年)
熟練の技術者として後輩の指導と現場管理を任される職長になると、現場全体の品質や納期、コストを管理する責任が生じます。よって現場の職人を束ねるマネージメントスキルも必要です。
また、施主や元請け業者とのやり取りも担当するため、コミュニケーション能力も求められます。
年収の目安
・月収:40万円~50万円
・年収:約500万円~600万円
経営者・独立(10年〜)
独立し、法人として塗装会社を経営する場合、社員の給与管理、クライアント対応、資材の仕入れ、採用活動など、技術職であると同時に経営者としての力量が問われます。
また、独立しなくとも、働いている会社の経営陣として働く可能性もあります。
経営者として規模の拡大を目指すのか?それともM&Aで大きな会社の傘下に入るのか?といった、経営方針も決定します。答えがない分、難しい仕事ではありますが、給料もその分多くなっていくでしょう。
業績次第で年収は1,000万円を超えることもあり、企業規模によってはさらに高収入となります。
年収の目安
・月収:50万~100万以上(会社の規模や経営成績による)
・年収:約600万円~1,000万円以上
▼合わせてこちらもご覧ください▼
稼げる職人ランキングTOP10!収入アップのイメージや将来性まで
塗装工の資格にはどんなものがあるの?

塗装工の仕事を行う上で、資格は必須ではない場合もありますが、専門知識や技術、安全管理能力を証明し、実務において信頼を得るためには資格取得が非常に重要です。
実務経験と資格取得の両方を取得することで、一人前の塗装工になることができます。
具体的には下記の様な資格を取得すると有用でしょう。
| 資格名 | 種類 | 認定機関 | 主な対象者 | 特徴・メリット |
|---|---|---|---|---|
| 1級塗装技能士 | 国家資格 | 厚生労働省 | 7年以上の実務経験者 | 高度な技術を証明。現場責任者や職長としての評価に繋がる。 |
| 2級塗装技能士 | 国家資格 | 厚生労働省 | 2年以上の実務経験者 | 基本的な塗装技術を証明。スキルアップの第一歩。 |
| 有機溶剤作業主任者 | 国家資格 | 厚生労働省 | 有機溶剤を使用する作業に従事する人 | 健康被害防止のために必要。法定で主任者の設置が義務づけられている。 |
| 外壁診断士 | 民間資格 | 一般社団法人全国住宅外壁診断士協会 | リフォーム業従事者、塗装職人 | 劣化状況を専門的に診断でき、提案力の向上につながる。 |
| 高所作業車運転技能講習 | 技能講習 | 各地の労働基準協会など | 高所作業に関わる技能者 | 高所作業車(10m以上)の運転に必須。現場での即戦力に。 |
1級塗装技能士(国家資格)
1級塗装技能士は塗装工の技能を証明する資格です。
厚生労働省が認定している国家資格なので、自分の技能が高いことを表す資格として有用です。実務経験が7年以上ある技能者、または2級合格者で実務経験が2年以上ある者が受験資格を持ちます。
筆記試験と実技試験の両方があり、合格すれば高度な塗装技術を持った職人として認められます。公共工事や大手建設案件でも信頼される要素となり、昇進や職長登用にも有利です。
2級塗装技能士(国家資格)
2級塗装技能士も、塗装工の技能を証明する資格です。
1級と比較すると難易度が低めではありますが、基本的な技術力を証明する資格になります。受験するには2年以上の実務経験が必要ですが、指定の養成校を卒業していれば免除される場合もあります。
1級塗装技能士を目指す前段階として取得する人が多く、初級から中堅へのキャリアアップの第一歩として位置づけられています。
有機溶剤作業主任者(国家資格)
有機溶剤を取り扱う現場で必須となるのがこの資格です。
トルエンやキシレン、シンナーなどを含む塗料を使用する際、健康被害のリスクがあるため、法令により有資格者の選任が義務付けられています。講習を受講し、修了試験に合格することで取得でき、安全管理と労働災害防止に大きく貢献します。
現場では有機溶剤作業主任者を選任しなければならないことがあるため、この資格を持っていると重宝されるでしょう。
外壁診断士(民間資格)
外壁診断士は、建物の外壁の劣化状況を適切に評価し、リフォームやメンテナンスの提案ができる民間資格です。一般社団法人全国住宅外壁診断士協会が認定しています。
特に戸建て住宅やマンションの外壁改修工事の前には、この診断が重視されており、提案型の営業や現調業務にも有利です。現場レベルで必須の資格ではありませんが、営業や経営など、商流の高い業務を目指すのであれば取得した方がいいでそう。
高所作業車運転技能講習
高所作業車を操縦するには、労働局認定の技能講習を修了する必要があります。特に10m以上の高所作業車を運転する場合はこの講習修了が義務付けられています。
現場によっては立馬を使っていたり、脚立を使ったりすることもありますが、高所作業車を使っている現場も多くあります。筆者も技能講習修了者なので高所作業車を運転したことはありますが、各段に作業スピードがあがります。
会社によっては高所作業車の資格を取得するサポート(費用負担)をしているところもあるので、入社前にヒアリングしておくのもよいでしょう。
塗装工として一人前になるまでどれくらいかかるの?
塗装工として本格的に一人前と呼ばれるようになるには、一般的に3年から5年程度の実務経験が必要とされています。
ただし、これはあくまで目安であり、個人の習熟度や現場で得られる経験の種類、指導環境によっても大きく異なります。しっかりと経験を積ませてくれる会社や、教育をしっかりとしてくれる会社を選ぶと一人前になるまでのスピードを早めることができます。あとは自ら学ぶ姿勢や資格取得の意欲も重要です。
ちなみに、「一人前の塗装工」とは、周囲の指示がなくても現場ごとに最適な施工方法を選択し、品質や安全に配慮しながら効率的に作業を進められる職人を指します。
具体的には以下のようなスキルが必要とされます。
| 必要なスキル・能力 | 内容 |
|---|---|
| 材料や道具の知識 | 塗料や下地材、刷毛やローラーなどの特徴を理解し、最適に使い分けることができる |
| 養生技術 | 建物の構造に応じて、不要な部分を汚さずにきれいに養生する技術 |
| 塗装技術 | 刷毛・ローラー・吹き付けなど様々な施工方法を扱える |
| 品質管理 | 塗りムラや剥離が生じないように管理しながら塗装を進められる |
| 現場対応力 | 天候や建物の状態、他の作業者との兼ね合いなど、臨機応変に対応できる |
| 安全管理 | 足場や高所作業、塗料の扱いにおいて安全意識を常に持ち続ける |
塗装工のやりがいや魅力は?

自分の仕事の成果が明確で美しい
塗装工の魅力のひとつは、自分の仕事の成果が目に見える形で残ることです。
塗装によって建物の老朽感が一新され、鮮やかで清潔な外観に生まれ変わったときの達成感は格別です。色や光沢の仕上がり、細かい部分の処理など、自分のこだわりが反映される分だけ満足感も大きくなります。
特に戸建住宅や公共施設、商業施設など、自分が携わった建物を日常生活で目にする機会があると、大きな誇りにつながります。
こだわりを持って仕事ができる
塗装工の仕事では、ただ色を塗るだけでなく、塗料の選定や下地処理、乾燥時間の管理など、多くの工程において精密な判断と技術が求められます。
それにより、ひとつひとつの現場ごとにこだわりを発揮することが可能です。現場の材質や気候、用途に合わせた最適な施工を施すことで、職人としてのスキルが磨かれ、唯一無二の仕事が届けられる点にやりがいを感じる人も少なくありません。
自分が携わった現場が増えていくのが楽しい
塗装工として働き続ける中で、住宅や公共インフラ、工場や大型商業施設など、自分の手で仕上げた現場が増えていくのが実感できます。
自らが仕上げた建物を街中で見かけたり、知人に紹介できたりと、成果が地域社会に根を張っていく様子は仕事のモチベーション維持にもつながります。
あとは、自分の住んでいる場所の周りで現場(思い出の地)が増えていくのも、建設業界で働く醍醐味です!
キャリアアップすることができる
塗装工は、実務経験を積むことで一級・二級塗装技能士などの国家資格を取得できるほか、現場監督にステップアップすることや、将来的に独立し会社を持つといったキャリアパスも描くことができます。
技能や実績が評価されやすい職種であるため、努力や技術が報酬や地位に直結しやすいのも魅力です。
安定して継続的に働くことができる
建設業界において塗装の需要は常に一定数あり、戸建住宅やマンションの外壁塗装、公共工事、商業施設の改修工事など、老朽化した建物のメンテナンス需要が年々増加しています。
そのため、腕のある塗装工は引く手あまたで、仕事がなくなる心配は少ないといえます。特に高齢化が進む中で経験豊富な職人の価値が高まっており、長く安定して働くことが可能です。
塗装工に向いている人のチェックリスト
以下の様な項目に当てはまる人は塗装工として活躍できる可能性が高いです。
・体を動かすのが好き
・安全意識が高い
・几帳面な性格
・体調管理ができる
・細かい作業が得意
・色の感覚がある
・ものつくりが好き
もし3つ以上当てはまるなら、塗装工に向いている可能性大です!
塗装工になるための具体的なステップ
ステップ1:未経験OKの企業に就職する
・建設業界では未経験歓迎の会社も多く、お仕事をしながら専門性と実務経験を積むことができます
・まずは求人サイトや会社のホームページ、ハローワークなどで情報を集める
ステップ2:現場の実務経験を積む
・最初は先輩社員のお手伝いから始めて、現場の工具や工法など、専門用語を覚える
・徐々に自分でできることを増やしていき、任される範囲を増やしていく
ステップ3:資格取得を目指す
・現場での実務経験を積むことができたら資格取得を目指しましょう
・実務経験と国家資格の両方を持つことで一人前の塗装工になることができます
塗装工の将来性と今後の展望
塗装工の将来性は高い、というのが結論です。
建築業界全体が人手不足や高齢化といった課題を抱える中、塗装工の需要は今後も安定して続くと予想されています。近年ではインフラの老朽化対策や外壁塗装のリフォーム需要が増加しており、塗装工の役割はより重要性を増してきています。
また、塗装業界としては環境に配慮した塗料の需要も増加しており、評価は今後さらに向上すると予想されます。
ITの文脈においても3Dスキャニングやドローン撮影による現場調査、自動塗装機の導入が始まっています。これにより、塗装工にはITリテラシーやデジタル機器の操作スキルも求められるようになるため、若年層にとっても魅力的な職業となりつつあります。
塗装工という職業は、時代に合わせた技術進化と社会ニーズの変化によって、より専門性が求められ、多彩なキャリアパスと安定的な雇用が保証される分野です。AIやロボットの導入が進む一方、職人の「手仕事」による品質が重視される場面も依然として多いため、人間の繊細な感性と技能が活かされる将来も続くと考えられます。
建築・リフォーム業界の中でも、塗装工は将来的にも安定した需要があり、若手や未経験者にとってもやりがいと成長が期待できる職種といえるでしょう。
記事全体のポイント
・塗装工は未経験からでも挑戦でき、自分自身の専門性を身に着けることができる
・専門性を身に着けることにより給料増加を見込むことができる
・将来的にも塗装工の仕事は重要であり、安定的にお金を稼ぐことができる
・経験を積むことで管理職や独立、経営者へのキャリアアップも見込める
塗装工の仕事は社会貢献性が高く、将来性もありキャリアアップも見込める魅力的な仕事です。
興味のある方は是非、塗装工の仕事にチャレンジしてみてください。
日成工業株式会社では塗装工を募集中
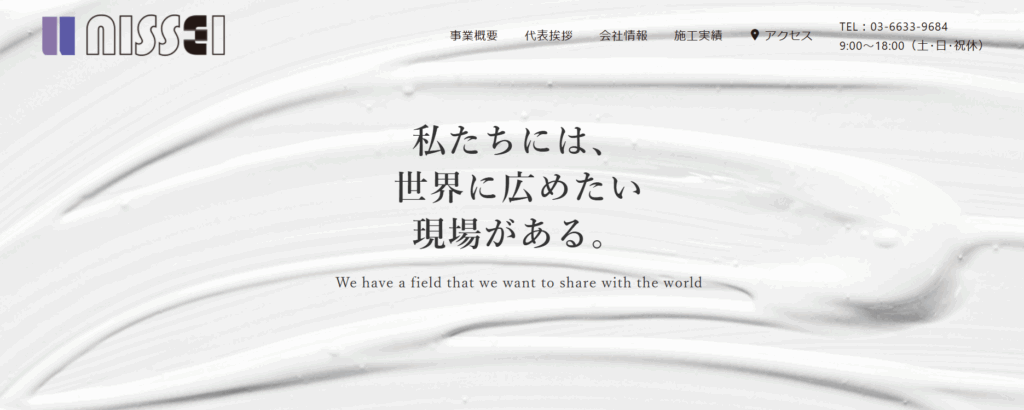
日成工業株式会社では、未経験から一人前の塗装工になる環境が整っています。
創業してから70年の歴史を持つ日成工業ならではの技術力と安定性が強みです。実務経験を積み、資格を取得することもできますので、安心して塗装工としてのキャリアを作ることができます。
また、親会社エルラインでは技術継承を目的としたエルラインアカデミーという教育制度があり、日成工業としても受講することができます。
まだ「塗装職人になることは決めていない」「転職するかどうかもまだ悩んでいる」そんな方でもOKです。
塗装工としての第一歩を踏み出そうか悩んでいる方は是非、下のお問い合わせフォームからご連絡ください。
お待ちしております。














コメント